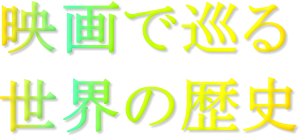ベルサイユのばら(2024年)

DATE
THE ROSE OF VERSAILLES/日本
監督 : 吉村愛
原作 : 池田理代子『ベルサイユのばら』(集英社「マーガレットコミックス」)
<主なキャスト>
オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ : 沢城みゆき
マリー・アントワネット : 平野綾
アンドレ・グランディエ : 豊永利行
ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン : 加藤和樹
アラン・ド・ソワソン : 武内駿輔
フローリアン・ド・ジェローデル : 江口拓也
ベルナール・シャトレ : 入野自由
ルイ16世 : 落合福嗣
ジャルジェ将軍 : 銀河万丈
……etc
目次 |
| 『ベルサイユのばら(2024年)』の作品解説 |
| キーワード『バスティーユ牢獄襲撃(1789年)』 |
| 『ベルサイユのばら(2024年)』のストーリー |
| 『ベルサイユのばら(2024年)』の感想 |
【作品解説】
革命期のフランスを舞台にした池田理代子による不朽の名作少女漫画の劇場アニメ化作品。原作は1972年から1973年まで集英社の週刊マーガレットで掲載され、1974年に初演の宝塚歌劇団の舞台化の成功などによって社会現象となり、1979年から1980年にはアニメ化もされた。2022年9月に誕生50周年を記念した完全新作の劇場アニメの制作が発表され、2025年1月に劇場公開された。
ルイ14世(1638年〜1715年)の時代、フランスでは諸侯の権力が低下し、国王の権力があらゆる権力に優越し、その絶大な権力によって王権による中央集権化が図られる――いわゆる絶対王政と呼ばれる政治体制が確立される。ルイ14世の時代から度重なる対外戦争やヴェルサイユ宮殿の建造(1682年)などによって出費がかさみ、ルイ15世(1710年〜1774年)の頃にはイギリスとの戦争によって戦費が国庫を圧迫したうえ多くの植民地を失うことなった。ルイ15世の死後、若干20歳のルイ16世(1754年〜1792年)が国王となる。フランスは1778年にアメリカ独立戦争(1775年〜1783年)に参戦したが、勝利の代償としてフランスの財政難は決定的なものとなった。
この頃の国王を頂点に聖職者(第一身分)、貴族(第二身分)、平民(第三身分)という封建的な社会制度のことを旧制度(アンシャンレジーム)と呼んだりする。第一身分、第二身分は税金を免除されたり、高い官職に就けたり、広大な土地を所有するなどの特権が与えられ、全人口の98%を占める第三身分は土地を持つ貴族の下で重労働に従事し、国税のみならず領主や教会への重税が課せられるなど苦しんでいた。民衆の不満は、第三身分の苦しい惨状などお構いなしに贅沢の限りを尽くす特権階級へと向かっていく。ルイ16世はローヌ男爵ジャック・テュルゴーや銀行家のジャック・ネッケルら経済に詳しい人物を登用して改革を推進しようとした。1776年に財務長官となったネッケルは、1781年に「国王への財政報告書」によってフランスの国家予算を公開し、王家の浪費や特権階級への優遇などが明らかにした。スイス出身の外国人で、貴族階級ではなくブルジョア階級――つまり第三身分であったネッケルは、民衆からの高い支持を得たが、ネッケルが推し進めようとした改革は利権を手放すことを拒否特権階級からの激しい反発を招き、「国王への財政報告書」の公表直後に罷免された。その後任者たちも、特権階級への課税などを行おうとしたがことごとく失敗した。
1788年、再びネッケルに登板の機会が巡ってくる。ネッケルは財政改革を推し進めるために世論を味方につけなければならないと三部会の開催を国王に求め、自身の財務長官就任の条件とした。いつまでも改革が進まない現状を打破したいルイ16世も、三部会の開催を認めた。三部会は第一、第二、第三の各身分の代表が集まり、重要議題を議論する場であった。特権階級の聖職者や貴族たちも、三部会を利用して絶対王政が確立される過程で王権に奪われた権力や特権を取り戻そうと画策していた。それぞれの思惑が重なり1789年5月に174年ぶりに三部会が招集された。しかし、この三部会は第三身分の期待を踏みにじるものに終わった。議決方法などを巡って三部会は空転し行き詰まり、改革を潰したい特権階級と第三身分の対立は深まるばかりだった。第三身分の代表者たちは「自分たちこそ国民の代表である」として国民議会の開催を宣言。6月20日に、「憲法制定まで国民議会を解散しない」と徹底抗戦を誓い合った(球戯場(テニスコート)の誓い)。当初は国民議会を弾圧して解散させる方向に動いていたルイ16世であったが、聖職者の多くと一部の貴族が国民議会に合流。ルイ16世は国民議会と宮廷の対立が起こることを懸念し、最終的には国民議会を承認し、最後まで国民議会に反対していた聖職者や貴族にも合流するように要請した。国民議会は7月9日に憲法制定国民議会に改称され、憲法制定に向けて動き始める。
財務長官ネッケルはルイ16世が身分間の対立の調整役を努めることを期待していた。ルイ16世も財政改革の必要性は重々理解していたが、宮廷内の反改革の強硬派が大勢を占めるようになっており、ルイ16世の意向も通らなくなっていた。宮廷の強硬派は軍事力によって国民議会を解散しようと企み、軍隊を招集した。これに対し、市民の中にも民兵隊を組織する動きが出て、アメリカ独立戦争で義勇兵を率いたラ・ファイエットが司令官となった。7月11日にパリに2万の軍隊が集結し、宮廷はその武力を背景にネッケルを罷免した。12日、民衆から人気の高かったネッケルが解任されたという報に、パリの市民は憤激すると同時に、軍隊によってパリが制圧されるのではないかという不安を抱いた。パリ各所で騒動が発生し、不穏な空気に包まれる中、14日朝、大勢の群衆――その数は7千〜8千人とも、4万〜5万人とも言われる――が廃兵院に押し寄せ、武器弾薬の引き渡しを求め3万2千丁の小銃と20門の大砲を奪った。
群衆はさらに武器弾薬を得るためにバスティーユ要塞(監獄)へと向かった。市民の代表3名が武器弾薬の引き渡しの交渉を行う。バスティーユ要塞はかつては政治犯を収容していたアンシャン・レジーム支配の象徴ともいえる監獄だったが、この頃にはその役割を終え、政治犯とは関係のない囚人が7人収容されているだけだった。群衆も、政治的意図や国家権力への抵抗の象徴としてバスティーユ要塞を狙ったのではなく、数日前に武器弾薬が持ち込まれたという噂があったからだった。要塞守備隊司令官のベルナール・ド・ローネーは代表を招き入れて食事を振舞い歓待したが、武器弾薬の引き渡しは拒否し、交渉は難航した。そうこうしている間に、群衆の数は増えボルテージが上がっていった。
要塞の守備隊は正規兵に満たない退役軍人80人と、応援としてスイス人傭兵30人が配備されていた。交渉が長引く中、しびれを切らした群衆の一部が跳ね橋の鎖を切って要塞に侵入。守備隊側は警告の後、発砲した。午後1時頃であったという。これを、きっかけに群衆と守備隊の間で戦闘が始まる。しかし、午後3時半頃にフランス衛兵隊の一部も群衆の側につき、守備隊側は劣勢になっていく。戦闘は4時間に渡り続いた。司令官のド・ローネーは籠城ができる態勢が整っていなかいこともあり、これ以上の戦いは無理と判断し、要塞内の人間の身の安全が保証されることを条件に降伏を決意する。一説では、この条件が受け入れられられなかったド・ローネーは要塞を爆破しようとしたが守備兵に止められたとも伝えられている。午後5時、守備隊からの発砲が止まり、戦闘は終結した。
バスティーユ要塞での群衆と守備兵の戦いでは、群衆側には約100人の死者が出たが、守備隊側の死者は1名にとどまった。しかし、守備隊司令官のド・ローネーは、市庁舎まで連行される途中で群衆によって集団リンチを浴び、殺害されて首を斬り落とされた。ド・ローネーの首は槍の先に掲げられて数時間にわたって市中を練り歩かれて晒し物にされ、翌日セーヌ川に捨てられたという。守備隊の3人の士官と3人の兵士も群衆によるリンチの末殺害され、2人のスイス人傭兵が行方不明となった。また、パリ市長のジャック・ド・フレンセルも、射殺されて首を斬られ、ド・ローネーと並んで晒された。パリに終結していたスイス人傭兵を中心とした2万の軍隊は、この事態に何の手も打たないまま、14日夜にヴェルサイユへと撤退した。軍の指揮官であったブザンヴァル男爵は、旧体制の支持者から裏切り者扱いされ非難され、以降は名声を失い、1794年にパリで死去したという。
パリ市民が蜂起しバスティーユ要塞を襲撃したという報せはルイ16世のもとにも届けられた。ルイ16世はこの日の日記に「特になし」と記した、という。また、報を受けたルイ16世は「暴動か?」と側近に問い「いいえ、陛下、革命です」と返された、などという逸話が残されている。バスティーユ要塞襲撃を端緒に、パリではブルジョア階級が市政の実権を握った。農民が蜂起し領主の館を襲撃するなど、旧体制に対する不満が全国で一斉に吹き出し、不安に駆られた領主の側も農民を虐殺する事件が起きるなど、混乱が広がった。宮廷の強硬派の中にも、フランスを離れて他国に亡命する動きが広まった。しかし、この頃はまだ、国王に対する敬意は残っており、これらの動きは王政の打破を目的としたものではなかった。バスティーユ要塞襲撃の翌日に、市民軍の記章が制定されたが、それはパリ市のシンボルカラーである赤と青、それにブルボン王家の白を挟んだものになっており、後のフランス国旗のルーツとなった。バスティーユ要塞襲撃は民衆が自由のために立ち上がったフランス革命の始まりとして認識され、現在も7月14日はフランスの祝日として、毎年祝典が開かれている。
1770年5月――。混迷の度を深めるヨーロッパ情勢を見据え、フランスとオーストリアは同盟関係をより強固なものとするために、フランス王太子ルイとオーストリア皇女マリー・アントワネットの婚姻を結ぶこととなった。フランスへとやってきたマリー・アントワネットは、警護についている近衛連隊付きの大尉、オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェが女性だと知って驚く。オスカルは、名門将軍家の娘であったが、後継ぎとして男として育てられ、その凛とした佇まいから貴婦人からの憧れの的だった。そんなオスカルとともに成長した平民で使用人の息子のアンドレは、オスカルに言葉にできない感情を抱いていた。
異国の宮廷で孤独を深めるマリー・アントワネットは、夜中に宮廷を抜け出して舞踏会に参加するようになる。そこで出会ったスウェーデンの若い貴族、ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン伯爵に淡い恋心を抱く。後日、改めて宮廷を訪れたフェルゼンとマリー・アントワネットは再会する。マリー・アントワネットが暴走した馬の事故に巻き込まれ、その咎がアンドレに向けられる事件が起こる。オスカル、フェルゼン、マリー・アントワネットの助命嘆願によってアンドレは命を救われ、4人の若者は絆を深める。やがてルイ15世が逝去。新たな国王となったルイ16世と、皇后となったマリー・アントワネットを国民は歓喜を持って迎えた。
それから数年――フランスの財政は悪化の一途を辿り平民たちは塗炭の苦しみを味わっていた。その怒りは貴族と――贅沢を惜しまない皇后マリー・アントワネットに向けられた。さらに、マリー・アントワネットとフェルゼンとの秘められた愛。オスカルは立派な皇后になってもらいたいと忠告したものの、マリー・アントワネットの寂しさや苦しみに気付いていなかったことに愕然とする。オスカルはアンドレと馬車で移動中にパリの平民と貴族の騒動に巻き込まれる。激高した平民からオスカルを庇ったアンドレは左目を失明してしまう。これをきっかけに平民のことを知らなければならないと感じたオスカルは、近衛連隊を辞してフランス衛兵隊へと入隊する。平民出身の衛兵隊の隊士に、女であり貴族であるオスカルは軽んじられるが、彼らと正面から向き合い、認められる。
パリの情勢は悪化の一途を辿っていた。危険極まりない衛兵隊から離れさせようと、オスカルの父はオスカルを結婚させようと試みるが、そのことでオスカルはアンドレへの言葉にできない想いを自覚する。マリー・アントワネットもまたオスカルを近衛連隊に呼び戻そうとする。毎日のように起こる平民の暴動を鎮圧するために、パリには国王の軍隊が向かっていた。オスカルは、国民を守るための軍隊の銃を国民に向けてはならないと反対する。平民の暴動を下賤な平民議員の扇動によるものと決めつけ、王権を神から与えられた不可侵なものだと言うマリー・アントワネットに対し、オスカルは別れを口にする。
実を言うと「ベルサイユのばら」は原作もアニメも宝塚も見たことがない。とはいえ、10巻にも及ぶ原作を112分に収めるのは大変だっただろう、というのは予想がつく。一つ一つのエピソードは短くダイジェスト版のような薄さを感じるし、キャラクターの心情を楽曲を使いミュージカル調で表現しているのは随分な力技という気もするが、それでも長大な作品を綺麗にまとめていたと思う。
フランス革命へと至る平民の苦しみやマリー・アントワネットが国民の敵へとなっていく過程や心情を、もう少し丁寧に描いてほしかったと感じるので、前後篇で制作するなりしてもう少し尺を取って欲しかったと思う。原作のファンがこの映画にどのような評価を下したのかは分からないが、原作や旧テレビアニメの入り口としてはいい作品だったと思う。